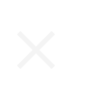「Number」でも活躍しているスポーツカメラマン・藤田孝夫は、主に陸上、水泳、体操といった個人競技を撮影している。カメラの世界に足を踏み入れたのは、18歳の時。きっかけは野球部員だった高3の春、初めて観戦したテニスの国際大会だったという。
「イワン・レンドル、トレーシー・オースチンといった世界的なスターが出ていて、お客さんも勝ち負けだけではなく純粋に選手のプレーを楽しんでいました。『こんな世界があったんだ』と、目の前が開けた瞬間でした」
ただ、藤田少年の目にはテニスの試合だけでなく、その視界を遮るような位置に陣取ったカメラマンの背中がちらちらと映った。
「その時、『カメラマンになればスポーツをもっと近くで見られるんじゃないか』と考えたのが、この仕事を志したきっかけです。今思えば邪な動機ですが、そのくらいスポーツが好きだった」
個人競技の選手を撮りたい理由
スポーツカメラマンになると国内外でさまざまな競技を撮り続け、今や撮影で訪れた国の数は50を超える。「こんなところにも藤田さんが」と同業者からは神出鬼没を驚かれているが、藤田の中ではひとつの軸があるという。
「個人競技の選手を撮りたい、という思いは常に持っています。自分が野球という団体競技をやっていたせいか、たった一人で期待や勝敗を背負っている個人競技の選手が眩しく見えるんです。常套句のように使われる『自分との闘い』という言葉が、彼らにはまさしく当てはまる。写真を撮っていると、本当に自分と戦っていることがレンズ越しにひしひしと伝わってきます。また、一人の選手がデビューしてから引退するまで追い続けることもできる。選手の人としての変化や成長を目の当たりにできることも、この仕事の醍醐味ですね」
スポーツシーンを撮るのではなく、あくまでスポーツしている「人」を撮る。だから勝者の勇ましいガッツポーズばかりではなく、敗者の肩を落とした背中も撮ってきた。勝敗だけにとらわれず、その試合に至るまでの「自分との闘い」が伝わるような写真が理想だ。
「スポーツ写真は、ゴールの瞬間やガッツポーズを誰が一番うまく撮れるか競うものではありません。例えるなら、ビーチ・フラッグスのように1本の旗を奪い合うのではなく、みんなで一斉に砂を掘り返して『僕はこんなものを見つけた』と成果を見せ合う“宝探し”に近い」
千葉すずとの出会いで考えさせられたこと
藤田にとって印象的な被写体の一人が、競泳の千葉すずだ。Number Webの記事(千葉すずが教えてくれた「距離感」。メディアから逃げる彼女との1対1。)でも書いているように、選手とカメラマンの関係について考えさせられる存在だったという。
「僕が千葉すずと初めて言葉を交わしたのは、1994年の世界水泳ローマ大会。練習時間に、その日は出場予定のなかった千葉すずがプールに現れて、水にちょっと浸かっただけで上がろうとしたから、思わず『もう上がり?』と声を掛けました。彼女は『この人、私に話しかけてきた!』みたいな、怪訝な表情を浮かべていましたね。当時の千葉すずはメディアと距離を置いていて、腫れ物に触るような感じであまり話しかける取材者はいなかったんです。その日を境に、大会会場で会えば話すようになりました」
千葉すずは集団行動を嫌うようなところがあり、個人競技の競泳選手の中でも特に孤独に見えた。写真から誰よりも「自分との闘い」が鮮明に浮かび上がる千葉すずに、藤田は興味を持つ。それから藤田はプールに通い続け、やがて千葉すずにとってそこにいるのが当たり前の存在になっていった。選手がカメラマンを意識しなくなったときこそシャッターチャンスだと、藤田は考えている。
「僕のカメラに向けてこういう表情をしてほしいとか、そういう思いは一切ない。練習中もカメラのことを意識しないでいてくれれば、それが『自分との闘い』を撮るためにはベストですからね」
千葉すずのように練習から見続けた選手が本番を迎える時、スタート前の藤田の心境はどのようなものなのか。
「もちろん、緊張しますよ。仕事として『撮り逃してはいけない』という緊張もありますが、その選手の過程を知っていればなおさら緊張します。でも、個人競技はそうやって楽しむものですから。知らない人たちが泳いでいても『速いな』としか思わないけれど、誰と誰がライバルで、あの選手はこの前の大会で負けていてとか、背景を知っていればより楽しめる。楽しみの量を見る側が決められるのが、個人競技だと思うんです」
フィルムからメモリーカードに変わって
今では機材の進化で、技術的には誰もが良い写真を撮れるようになりつつある。仕事を始めた頃はフィルムカメラで撮っていた藤田も、2000年代からはデジタルカメラで撮るようになった。
「フィルム1本は36カットを撮ったら交換しなければならないので、スタートからゴールまでどの瞬間でシャッターを切るかというマネジメントが必要でした。それがスポーツ写真の難しさであり、カメラマンの個性が表れる部分でもあった。記録媒体がフィルムからメモリーカードとなった今はいくらでも連写できるので、その難しさはありません。カメラマンの腕の見せ所が減ったことに複雑な気持ちもありますが、読者にお届けできる写真は格段に増えました。これまで撮れなかった瞬間も撮れるようになったので、読者にとって撮影機材の進化は良いことしかないんです」
サンディスク製品がカメラマンに愛される理由
そうして撮ってきたスポーツ写真は、膨大な枚数になった。競泳の大会でいえば、1日でおよそ2000カットを撮るため、撮影データの管理には慎重にならなければいけない。藤田は撮影を終えると、メモリーカードに記録された写真データをポータブルSSDに保存している。
「15年くらい前から、サンディスク製品を使っています。ストレージを信頼しているからこそ、緊張する試合でも思い切って撮影に臨める。これまでトラブルに見舞われたことはないし、サンディスク製品が世界中で販売されていることも海外取材の多い僕にとっては心強い」
サンディスクはメモリーカードの登場当初から、カメラメーカーとともにカードの規格の策定を担ってきた。そのため、同社のメモリカードは、さまざまな機種のカメラと互換性がある。また、デジタルカメラの進化と歩調を合わせ、常にその時点での最速、最大容量のメモリーカードを開発してきた。いつの時代も最新カメラの性能を存分に発揮させてきたことは、サンディスク製品が多くのカメラマンに愛される理由のひとつだろう。
桁違いの書込みスピード
藤田が現在使っているカメラはCFexpressカードに対応しているため、サンディスクの「エクストリーム プロ CFexpress Type Bカード」を入れて撮影している。
「このメモリーカードの書込みスピードは、1400MB/秒と桁違いです。スポーツのスチール写真撮影ではそこまで必要ないかもしれませんが、高解像度の動画撮影では最大の力を発揮するでしょう。また、読取り速度も1700MB/秒と高速です。同じく高速転送が可能なサンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDと併用することで、作業が非常に効率化されます。撮影後、データを素早く雑誌編集部に送らないといけない場合には必須ですね」
同時に、藤田はすべての写真をサムネイル印刷したファイルも作っているという。1冊80ページほどのファイルが、今では400冊近くなった。
「撮影データはすべてデジタルで、SSDに大量のデータが保存できるといっても、物理的にパッと写真を一覧できるこのファイルは、何だか安心するんですよね」
アナログで骨の折れる作業ではあるが、これによって自分が撮った写真を正確に把握することができ、「Number」など雑誌編集部からの依頼にも、すぐに写真を送ることができるという。
写真を撮り、それを読者に早く確実に届けること。それが藤田にとって、スポーツカメラマンとしての「自分との闘い」だ。
「Sports Graphic Number」より転載

Number編集部
Sports Graphic Number
Takao Fujita